奇妙な話を紹介する奇譚展へようこそ。
今回は黒澤いづみ『人間に向いてない』のあらすじと感想を紹介します。
あらすじ
ある日、一人息子である優一の部屋を開けた美晴は、一夜にして巨大な芋虫のような生物になってしまった息子の姿を発見する。
数年前から突如流行し始めた「異形性変異症候群」は、人間が何の前触れもなく異形の姿に変貌してしまう病気だ。原因不明、治療方法不明の奇病に冒された者たちは、社会から実質的な死者として扱われる。
息子の変わり果てた姿を前に絶望する美晴だったが、大切な息子を見捨てることはできず、変異した家族を持つ人同士が交流する「みずたまの会」に参加することを決意する。
若者が異形の生物に変貌する奇病

ある日、息子の優一の部屋から「かしかし、かしかし」と何かを引っ掻くような音を聞いた美晴は、恐る恐るドアを開けて中に入ります。カーテンが閉ざされたままの薄暗い部屋の中で見つけたのは、巨大な芋虫のような体に、ムカデのような無数の脚をもつおぞましい生き物でした。
本作では、人間が突如として異形の姿に変貌する奇病「異形性変異症候群(別名:ミュータント・シンドローム)」が大流行する社会が描かれています。全国各地で数万人の患者が出ているというこの病気には、一つの注目すべき特徴があります。それは、この病気に罹るのが若者ばかりで、その中でも特に引きこもりやニートと呼ばれる層の若者たちばかりが罹る病気だということです。
22歳になる優一も長い間働かず引きこもりの状態が続いていたため、美晴自身、いつか息子がこの奇病に罹ってしまうのではないかと日々怯えていました。異形の生物を発見して恐怖に慄いた美晴でしたが、それと同時にこの生物が間違いなく息子であるということも確信せざるを得なかったのです。
目の前のこれはどこからどう見ても異形だ。虫に近いデザインではあるものの、中型犬ほどの大きさひとつとっても、およそ一般的な生命体とは言いがたい。震える美晴の目の前で、『それ』はしゃりしゃりと顎を動かした。
黒澤いづみ「人間に向いてない」(2018)講談社
奇病をめぐる社会の混乱

この前代未聞の奇病に国も人々も大混乱します。病気であるかぎり患者は手厚く保護されるべきですが、あまりにグロテスクな見た目のせいで世話することを放棄する人々が後を絶ちません。発症の原因も治療方法も不明なため、家族から見捨てられる患者が増えていきます。
中には思わず患者に暴行を加えて殺してしまうというケースや、患者の生命保険金を受け取ろうとして起きる殺人事件、病気が完治すると騙して商品を売りつける詐欺事件など、厄介なトラブルが次々と発生します。
奇病を発端とする様々な問題に困り果てた政府が最終的に決定したのは、「異形性変異症候群」を致死性の病とし、この診断が下された時点で人間としては死亡したものとする、というものでした。死因にはその病名が記され、患者の家族は遺族として役所に死亡届を提出する義務が課されます。それ以降、異形の生物は「変異者」として完全に人権を失い、人間として扱われることはなく、義務や権利から解き放たれる代わりに、野生の獣や虫とほとんど変わらない扱いになるのです。
たとえおぞましい姿になっても大切な我が子と離れる気持ちにはなれない美晴に対し、引きこもりだった息子に元々嫌気がさしていた父親の勲夫は、人として死亡した優一を早く見捨てようと主張します。
部屋の片すみでもぞもぞとうごめいている優一の耳に、勲夫の残酷なセリフがもし聞こえていたらと思うとあまりにも切なくなります。
今までだってできることなら棄てたかったが、体裁もあって許されなかった。だが今のこいつはもう人間じゃないからな。何の法も適用されないんだ。たとえ何をしたとしても。
黒澤いづみ「人間に向いてない」(2018)講談社
変異者の家族が交流する「みずたまの会」

どんな理由があっても親として自分の子どもを見捨てることは許されないと考える美晴は、勲夫を何とか説得し、これまでどおり優一と暮らし続ける生活を選択します。そして「異形性変異症候群」について色々と調べていくなかで、異形の姿に変貌した「変異者」を家族に持つ者同士が交流できる「みずたまの会」の存在を知り、入会することを決意するのです。
「みずたまの会」では、同じような悩みを抱える人が数多くいることに美晴は安心します。また、一口に「変異者」といっても、植物のような姿をしたものや、犬の体に人間の顔だけが残ったものなど、様々なタイプがいることを知ります。
さらに「変異者」を持つ家庭には、子どもたちが変異する以前から、それぞれ複雑な事情を抱えていたということもわかってくるのです。
異形性変異症候群―この奇妙な病気について、私はひとつの仮説を立てている。必ずしも変異した本人ばかりに問題があるのではなく、その親…ひいては家庭そのものに問題があって発症するのではないか、ということだ。
黒澤いづみ「人間に向いてない」(2018)講談社
【考察】人間に向いていないのは誰なのか
美晴をはじめ、本作に登場する親たちは、グロテスクな姿に変貌した我が子を受け入れるのか見捨てるのかという究極の選択を迫られます。子を持つ親であれば考えたくもないような状況です。
本作では、常識的にはありえないような奇病の存在を通じて、引きこもりやニートといった若者を生み出している現代の社会や家族の闇に迫ります。物語の中の親たちは皆、我が子が異形の姿になってはじめて、それまで目を背けてきた家族の問題と向き合うことになるのです。
美晴もこの奇病をきっかけに、優一が引きこもりになってしまったのは親である自分たちのせいなのではないかと自問自答を繰り返します。果たして人間に向いていないのは、異形となった子供たちなのか、それを生み出した親たちなのか、これは読む人によっても印象が異なるところかもしれません。
子どもにとって唯一であるはずの父母、誰よりも味方であるはずの親に否定され続ければ、歪んでしまうのも無理はない。異形の姿となる前に、心もとっくに異形になっていたのだろう。自分がただ自分として在ることを許されなかったのだから。
黒澤いづみ「人間に向いてない」(2018)講談社
人間が異形の生物に変貌する物語といえば、チェコの文豪カフカの『変身』という作品が有名です。本作はまさに現代日本版の『変身』とも言える作品ですが、『変身』では虫になる主人公ザムザの視点で物語が進む一方、本作では異形に変貌した子供の親たちの視点で物語が進むという点が異なります。
また、『変身』のザムザが仕事のことばかり気にする仕事人間だった一方で、本作では仕事をしていない引きこもりやニートの若者が変身するという点も対照的です。
一夜にして異形の生物に変身してしまうという同じような設定でありながら、話の内容が全く異なる二つの作品を読み比べてみるのも面白いかもしれません。

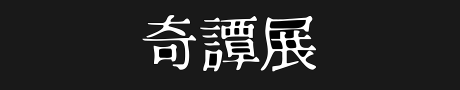



コメント