奇妙な話を紹介する奇譚展へようこそ。
今回は吉村萬壱『クチュクチュバーン』のあらすじと考察を紹介します。
あらすじ
ある日突然、地球のすべての秩序が壊れてしまった。人間たちは苦しみに悶え、共食いを繰り返しながら、動植物や無機物と融合して異形の怪物に変身していく。
まだ変身しきっていない人びとは、無秩序のもたらす不安のなかで、ひたすらあてもなく歩きつづけることしかできない。シマウマ男や蜘蛛女が闊歩する街、混沌のなかで権力を握る自警団や死体の「処理施設」……。
宇宙規模の「進化」に翻弄される人びとの姿の、グロテスクでありながらもどこか爽快感のある記録。
「見る」ことの危険な快楽
突如始まった謎の「進化」により、人間たちは理由も仕組みもよくわからないままに、次々と無惨な姿に変身していきます。
脇腹を突き破って生えてきた十本足で蜘蛛のように這う女、事務机と一体化して引き出しのなかに顔や性器を隠しもつ人、ハムスターほどの大きさに縮んだ男。次々と出てくる異形の者たちのグロテスクな姿は、目を背けたくなるものばかり。
しかし、読み進めるうちに、悲惨な状況にもかかわらずどこかユーモラスで不条理な彼らの姿や行動は、まるで見世物ショーに身を乗り出す子どもになったかのような、どこか不思議な高揚感を読者へともたらします。
実際、19世紀末から20世紀半ば頃にかけて世界的な規模で流行した見世物小屋では、貧しい子どもたちや障がいをもって生まれた人びとの姿が「蜘蛛女」「ゴム人間」などといった謳い文句で見世物にされ、多くの観客を集めていました。これが倫理に問題をかかえた商いであることはいうまでもありませんが、古くから処刑の見物が庶民の娯楽であったことからもわかるように、人間は暴力的なまでに「見る」快楽に対して貪欲な生き物です。
本作には、街にのさばる「自警団」たちが炊き出しの雑炊に毒を入れ、それを口にした人びとが次々と変身しながら悶死するさまを「極上の見せ物」として笑いながら見物する場面があります。極悪非道に見える彼らですが、この場面には興味深い記述がつづきます。
自警団たちは一定の逸脱行為をした後、ほとぼりを冷ますために一時的に解散するのが常であった。さもないと悪い空気が自分たち自身を滅ぼしかねないことを知っているのである。彼らは基本的に用心深く、強くもなく、本物の哄笑に生きているのでもなかった。喧騒に飢え、沈黙を忌避する臆病な人間が炊き出しの炎に身を寄せ合い、震えているに過ぎなかった。
吉村萬壱『クチュクチュバーン』(2005)文藝春秋、p.44
この描写からは、自らの「見る」暴力性に十分すぎるほど自覚的であり、自分のなかに抱え込んだその獣のような欲求に怯える自警団たちの姿が浮かびあがってきます。どこにでもいる小さな人間でしかない彼らは、ある意味で、ページから目を離せない私たち読者と同じ状況に置かれているのかもしれません。
【考察】この世界は一体何なのか?
論理を失った世界は「何もかも、意味不明」。人びとは死体を「処理施設」で加工して食品や日用品にするするほかなく、日常的に起こる突飛な変身の数々に疲弊しきっています。
この地獄のような世界は、いったい何なのでしょうか。
一見するとまとまりのない描写の連続に思える本作ですが、よく読むと、いくつかこの問いに答えてくれそうな記述があります。ここでは、ふたつの説を考えてみます。
- 奇妙な夢

作品世界を読み解く手がかりとなる記述のひとつが、中盤の「夢」の場面です。そこでは、かねてより自身の変身の兆しを恐れていた少女・マユがついに無数の虫へ変身を遂げる描写があったかと思うと、突如場面が切り替わり、それがマユの母の不倫相手の見ている夢であったことがわかります。
ところが、その後マユが登場することはありません。すなわち、マユが実際にどうなったかはわからないのです。するとこの物語全体が、誰かの見ている荒唐無稽な夢であると考えることもできるかもしれません。
しかし、その説を確信させてくれるほどの情報は与えられず、読者は宙吊り状態にされます。
- 「書く」という体験そのもの

ふたつめの手がかりは「シマウマ男」の体験です。シマウマと人間が合体した姿をもつ彼は、物語の初めから一貫して、世界の惨状を眼差しつづけます。
「俺の仕事は見ることだ」と語る彼は、あらゆるものがごちゃまぜになった世界で、蜘蛛女との奇妙な性交やブラックホールのような集合体への「融合」に巻き込まれながらも、ひたすらに見ることをやめようとしません。
とりわけ後者の「融合」の場面は、本作の世界を語る上で欠かせないものでしょう。あらゆる怪物たちがごちゃ混ぜになった塊のなかで、シマウマ男だけが不思議と意識を保っているのです。
彼は見ることを仕事としていたために、「存在することは見られること」の根本原理に従って、この唯一のモノを存在させるためだけにその存在を許され、ためにいつまでも未消化なのだった。おまけに自意識のようなものまで残っているのだ。
吉村萬壱『クチュクチュバーン』(2005)文藝春秋、p.86
「存在することは見られること」。
どんな物も出来事も、見る人がいなければ、実在を認識されることはありません。それは存在していないのと同じだという考え方もできます。このカオスな作品世界も、シマウマ男に「見られる」ことによって初めて存在するといえるでしょう。
すると、初めから終わりまで不条理な世界をひたすら「見つづける」すなわち「存在させつづける」シマウマ男の正体とは、この作品世界の最初の読者=著者である、と考えることもできるのではないでしょうか。
原稿用紙の上で、まさに「クチュクチュバーン」と音が聞こえてきそうなほどの過激な混合・生成を繰り返す作品世界。頭から原稿用紙へ次々と生まれてきてしまう怪物たちに翻弄されながらも、著者はそれを素直に書きつけ、「見つづける」ことをやめません。その意味で、本作の世界は「書く」という体験そのものを書いているともいえるでしょう。
愚直なまでに「書くこと」に正直な著者の思いは、混沌のなかで揉みくちゃにされたシマウマ男の叫びに重なります。
「考えてはならないぞ。俺は見るだけだ。考えるもんか。考えても、何一つ分かりっこないのだからな!」
吉村萬壱『クチュクチュバーン』(2005)文藝春秋、p.86
吉村萬壱先生の他の作品が気になる方はこちらからどうぞ。
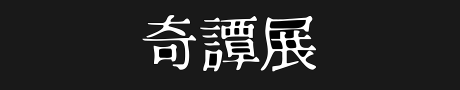



コメント