奇妙な話を紹介する奇譚展へようこそ。
今回は吉村萬壱の『ボラード病』のあらすじと考察を紹介します。
あらすじ
B県海塚市に母と二人で暮らす小学五年生の恭子は「鈍いタイプ」で、クラスや地域社会にうまく馴染むことができない。
周囲の目を異様に気にする神経質な母との軋轢、同級生たちの奇妙な死、そして海塚市民の心をひとつにする「結び合い」やボランティア活動を通して、恭子は復興の町と謳われる海塚市の異様な現実を目の当たりにしていく。
やがて母が病に倒れたことをきっかけに町の人々と関わるようになった恭子は、海塚市のかかえる病の最奥部に触れることとなる。
「結び合い」と同調への願望

物語の舞台は、八年前の災厄から復興しつつあるという海塚市。避難生活から戻ってきた住民たちは、故郷をよりどころとして皆の心をひとつにする「結び合い」の精神を重視し、それを強化するべく、ボランティアや清掃活動に励みながら生活しています。
恭子の通う小学校でも、「海塚賛歌」の唱和が強いられたり「りっぱな海塚市民になろう」という目標が掲げられたりと、愛郷心を育む教育が行なわれます。しかし、それは常に同調圧力と共にあり、劣等生の恭子は周りにうまく溶け込むことができません。
同級生のアケミが亡くなったとき、そのお通夜では、アケミの父が市民同士の「結び合い」の大切さについてスピーチします。「海塚」の合唱が高まるなか、特別な儀式を通して、アケミは「海塚市の一部」になったのだとまで言われます。
恭子はこうした海塚市のカルト的な習慣を、違和感や嫌悪感の入り混じる眼差しで語り続けます。
本作の視点は、それだけに留まりません。物語の後半には、周囲に同調することの安らぎについても語られる場面があります。
人の親切に甘え、世界を秩序だった美しい姿で見られる安心が手に入るならば、それが嘘や間違いだとわかっていても同調を積極的に選んでしまう。その結果、大きな集団全体が方向を誤り、取り返しのつかない破滅に向かう。これもまた、人間の普遍的な心理のひとつなのかもしれません。
このように本作は、社会が孕む同調圧力だけでなく、私たちの持つ「同調への願望」のグロテスクな姿をも克明に描いているといえます。
それは私たちにとって、同調圧力そのものよりもいっそう目を背けたくなるものであるだけに、目が離せないものでもあります。
母との間に流れる不穏な空気
「塀のどこかに小さな穴が開いていて、いつも見られているのだから、恥ずかしいことをしては駄目よ」
吉村萬壱「ボラード病」(2017)文藝春秋
恭子が他の人と違う言動をすると強く叱責して暴力を振るうこともある母は、神経質でどこか得体の知れない存在として描かれます。仕事を掛け持ちするほどに貧しい暮らしでも、「施設」に寄付すると言って野菜を余分に買ったり、異様なまでに虫嫌いで潔癖症であったり。協力しなければ生きていけない母子家庭だということは二人とも理解していながら、恭子と母の間には、常に不穏さと緊張感が漂っています。
小学五年生という時期は、子どもから大人へと移り変わる多感な頃です。物語の序盤では、母に反発心を抱きつつも叱られれば謝っていた恭子でした。しかし、母の内職の材料を届けに家へやってくる男性「川西さん」との出会いや、母の重い病により、少しずつ内面も変化していきます。
川西さんが自分のお父さんになればいいのにと願い、家族三人での団欒を夢見ると同時に、川西さんに恋心をも抱きはじめた恭子は、彼に笑いかける母に対して一人の女性として嫉妬し「敵意のようなもの」を感じるようになるのです。
海塚市の異常性を悟りながらも、潔癖で不器用な母にも限界を迎えつつあった恭子。第二次性徴に伴う自立心や反抗心も相まって、海塚市と母という二つの病の間でぐらついていた彼女の心は、海塚市の方へと傾きかけます。
しかし母の異様な厳しさにもまた、大きな理由があったのです。海塚市の同調圧力の中に置かれたとき、どこにでもある母と娘の軋轢の悲惨さは、より際立つのかもしれません。こういった観点から、本作は一読し終えたあと、恭子ではなく母を主人公として読むこともできる作品です。
【考察】最も恐ろしいのは見たままの世界?

「三十歳を越えた恭子が小学五年生の頃の頃を回想する」という本作の語りが持つ最大の特徴は、「です・ます」調で書かれた奇妙な世界です。
例えば、隣人の「野間又男」の表札を「ヌオトコ」と読む勘違いから、母の「岩のように大きなお尻」、いつもケージに体当たりして餌を強請るウサギのうーちゃん、網戸に張り付いているバッタと恭子自身の視点の入れ替わり、そして大人になるとお尻に毛が生えるという考えなど、可愛らしいものから不気味なものまで様々です。
こうした描写の数々は、「嘘は絶対に書きません」と大人になった恭子自身が語ることからも分かるように、子どもの頃に「見たまま」の世界を、彼女が素直に記録しているからこそなされるものといえるでしょう。
それは内面の描写においても同じです。わざと母に聞こえるように花に向かって話しかけ、その理由を「子供らしくて可愛いと思ったから」だと告白したり、内職に励む不器用な母を冷たい目で見たり、同級生に向かって「ざまあ見ろ」と心の中で吐き捨てたりする恭子の内面は、大人が期待する無邪気な子どもの姿からは程遠いものでしょう。しかし恭子は感じたままの思いを率直に記述しているのです。
一方、物語の序盤で彼女は、先生に教えられた「錯覚」という言葉が、「自分の秘密に属することだとピンと来た」のだとも言います。
そんな恭子が同級生や母や家を絵に描くと、母は怒ってそれを切り刻んでしまいます。そればかりか、誕生日プレゼントとして同級生の浩子に似顔絵を渡すと、浩子は恭子の首を絞めにかかるのです。
はたして恭子の「見たまま」の世界とは、周囲の人々にとっても同じように「見たまま」の世界なのでしょうか。それとも、恭子の「錯覚」にすぎないのでしょうか。
そして私たちの見ている世界もまた、誰かに見せられたものでない、私たちの「見たまま」の世界であるといえるでしょうか。
まとめ
今回は吉村萬壱の「ボラード病」を紹介しました。ボラードとは、船舶を繋留するための杭のこと。ぜひこのタイトルの意味についても考えながら読んでみてください。
吉村萬壱先生の他の作品が気になる方はこちらからどうぞ。
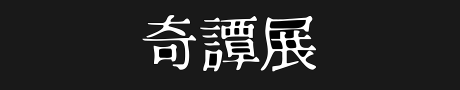



コメント