奇妙な話を紹介する奇譚展へようこそ。
今回は芥川賞作家・吉村萬壱『死者にこそふさわしいその場所』のあらすじと考察を紹介します。
あらすじ
250年もの伝統を持つ「捨て身祭り」に熱狂する地区・折口山。風に乗って町中を飛び回る護符に見張られているかのように、町民たちは祭りの準備に浮き足立つ。
しかしそのすぐ隣には、同じ地区に暮らす「どうしようもない人たち」の日々があった。どうしても朝起きられず出社もままならなくなった女、マゾヒスティックな信仰に溺れる新興宗教の支部長、家の扉を開け放ったまま寝て暮らす裸の巨漢……。
やがて彼らは祭りの喧騒を避け、町の廃植物園へ集まってゆく。
「どうしようもない人たち」の織りなす人間植物園

帯文に「奇『快』な人間植物園」とある通り、本作の登場人物たちはそれぞれに常軌を逸した奇人ばかり。それでも彼らのほとんどの狂気の根は、意外にも身近で真っ当な欲求のなかに張っているといえるでしょう。
例えば新興宗教の支部長・兼本が行おうとしていたのは「他者の世話になって生活する掛人=カカリュード」をお世話する、という一見道徳的な教義の実践でした。ところがエスカレートした彼の信仰はとどまるところを知らず、挙げ句の果てには右耳を切り取られ、顔に傷をつけられ、妻を身の危険に晒してまでも、その元凶であるホームレスたちを家に泊めてお世話をしては「有難うございます」と唱え続けます。
あるいは、どうしても朝起きられず会社に行けなくなってしまった「絶起女」こと高岡ミユの悩みも、誰もが抱えうる真っ当なものかもしれません。常に全力疾走を求める資本主義社会の速さについていくことができない彼女は、自らの寝坊と無気力を社会への「反抗」なのではないかとも考えますが、周囲からは「本物の精神病患者」とのレッテルを貼られてしまいます。
このように、いわゆる狂気に足を踏み入れつつも、どこか理解できそうな糸口を残した奇人たちが咲き乱れる「人間植物園」。しかしその中で、唯一謎に満ち、異彩を放っているのが「堆肥男」でしょう。
そこで次節からは、この「堆肥男」について考察してみます。
【考察】扉を閉めない「堆肥男」の謎
出版社に勤務する春日の住む格安アパートに引っ越してきた謎の巨漢は、ほとんど裸のままスナック菓子を貪ったり、スマートフォンで祭りの映像に興じたりするほかは寝てばかりという、怠惰な毎日を過ごしています。
そんな彼の家のドアは朝も夜も開け放たれており、コオロギやアライグマが入り放題のカオス状態。潔癖症の春日はそんな「裸男」を気味悪がりつつも、次第に目が離せなくなっていきます。
「裸男」の元には、ときどき背広の男やサングラスをかけた半被姿の男がやってきて、菓子やペットボトル飲料を差し入れているようですが、彼らと「裸男」の関係がどのようなものなのか、また「裸男」が何者なのかが明らかにされることはありません。彼の生活は珍妙で、家に入ってきた野良犬に糞を食われ、肛門を舐められて「ほほほほっ」と陽気な笑い声をあげていることもありました。
結局「裸男」は多くの謎を残したまま、春日の前から姿を消してしまいます。「裸男」が去ったあと、春日はかつて自分が仕事で取材した農家の老人の言葉を思い出します。
「人間なんぞ偉くも何ともないが、死んで土の肥やしになるっちゅう点だけは悪うない」
(…)裸男はきっと良い肥やしになるだろう。彼はそのことを思う度に、お気に入りの廃園の植物園が無数の花でいっぱいになっている光景を思い浮かべた。
吉村萬壱『死者にこそふさわしいその場所』(2021年) 文藝春秋
この場面でようやく初めて、「裸男」は章のタイトルでもある「堆肥男」として語られるに至ります。
有機物の死体が混ざり合ってできた堆肥とは、まさに家のドアを開け放って怠惰に生活するこの巨漢のように、内も外もない混合の果てに生まれるものであるといえるでしょう。
【考察】「堆肥男」と東千茅『人類堆肥化計画』
さて、ここで「堆肥男」の物語から一旦少しだけ離れ、同じく堆肥をテーマとした東千茅の著作『人類堆肥化計画』(創元社、2020年)に目を向けてみます。
里山で農耕をし、家畜を育てて暮らしている著者の東は、自らを「悪人」として、一見無欲で牧歌的に見える里山での農耕が、いかに暴力や腐敗をはらんだ快楽的な行為であるかを述べます。たしかに、自分が愛情をもって育てた作物や家畜を殺して食べ、またそれらに自分が生かされ養われているという事実だけでも、その生命の混じり合いは「堆肥」のありかたに接近するものでしょう。
『人類堆肥化計画』のあとがきによれば、「堆肥男」の物語は、東と吉村萬壱の対談から生まれたのだといいます。とすると、「堆肥男」もまた扉を開け放ちながら、自分と外の世界の境界が曖昧になり混ざり合っていく過程に、悪徳の喜びをもって浸りきっていたのかもしれません。
語り手は「堆肥男」?

本書のタイトルでもある最終章「死者にこそふさわしいその場所」では、「堆肥男」が実際に堆肥となり身体に草を生やす姿が描写されます。しかし、それよりも興味深いのが、それまで三人称小説として語られてきたこの物語に、突如「堆肥男」の語りとして「私」という一人称が登場することです。
すでに個体としての死を迎え、あらゆる有機物の混合する堆肥となった彼には、他の登場人物の頭の中がわかるらしく、まるでこれまでの「地の文」と同じような語りで、登場人物たちが描写されます。
さらに「捨て身祭り」の護符を依代としてこの世に留まっていると語る「私」は、「この街の土となった私が、今後折口山町の人々が祀る神々の中に付け加えられることは間違いない」とも言います。
これらの点から生じるのは、これまでの物語すべてが「堆肥男」の語りだったのではないか? という問いです。
堆肥は植物を育み、その植物は動物を養います。それら動植物もまた少しずつ堆肥となります。すなわち、堆肥とは世界と一体化しつつ世界を作りだす循環の根源でもあるのです。
「堆肥男」もまた「奇人=植物たち」に養分を送り、彼らと混ざり合うことで、この「人間植物園」に起こるそれぞれの物語をこっそりと窃視し、語っていたと考えることもできるのではないでしょうか。
「堆肥男」の物語に衝撃を受けたり面白がったりする私たち読者も、堆肥から貪欲に養分を吸い上げる植物のように彼の悪徳の喜びを吸い込み、「堆肥化」の第一歩を踏み出しているのかもしれません。
まとめ
今回は吉村萬壱の「死者にこそふさわしいその場所」を紹介しました。堆肥男の「生き様」に注目しながら、ぜひ一度読んでみてください。
吉村萬壱先生の他の作品が気になる方はこちらからどうぞ。
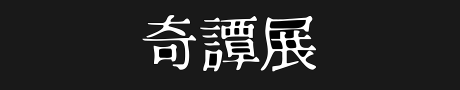



コメント