今回はカフカの代表作の一つである『流刑地にて』のあらすじと解説を紹介します。
あらすじ
とある流刑地で行われる処刑の立ち合いに招かれた旅行家は、処刑のために用意された特別な拷問機械を目にする。
その機械とは、処刑人を固定するための「ベッド」、鋼鉄製の針が取り付けられた「馬鍬(まぐわ)」、そして馬鍬を動かすための歯車が取り付けられた「製図屋」と呼ばれる三つの部分から構成されており、12時間ほどかけて処刑人の身体に針を刻む仕組みになっていた。
処刑機械について説明をしていた将校は、訪れた旅人にとある依頼をする。処刑機械に対して非人道的だと感じていた旅行家は、その依頼を断るのだが…。
自分の罪を知らぬまま処刑される罪人

流刑地での処刑に立ち会うことになった旅行家。彼が目にした不可解な装置とは「12時間もかけて生きたまま処刑人の身体に針を刻む」という奇妙な処刑機械でした。
もちろん旅行家は、生きたまま処刑人の身体に針を刻む非人道的な処刑方法を理解できませんでしたが、さらに理解に苦しんだのは「処刑人は自らの罪を知らされぬまま処刑される」ということでした。
旅行家はこれから処刑されようとする罪人を見て、自分自身の判決を知らされぬまま、罪人として機械に処刑される、この理不尽な状況を管理者の将校に説明を求めます。
しかし、将校から返ってきた答えは奇妙でゾッとするものでした。
「わざわざ告げてやる必要もないのです。当人のからだで知るのですから。」
フランツ・カフカ著, 池内紀訳『変身』(2006)白水社
「自分がどのような罪で処刑されるのか」、「その罪が適切なものなのか」ということも知らされず、仮に適切でないものだとしたらそれを弁明する機会も与えてもらえない。
現実では決してあってはならない奇妙で不条理な処刑が行われているのです。
自ら処刑機械へ〜不可解な結末〜
処刑執行を横目に将校は旅行家に対して処刑機械の説明を熱心に語ります。その口ぶりは異常であり「処刑機械を使って罪人を処刑する」ことが将校自身にとっての使命であると感じさせる勢いでした。
そもそもこの処刑機械を設計したのはすでに亡くなっている前司令官であり、現在の司令官はこの装置に対して否定的な考えを持っていました。つまり、処刑機械を支持しているのは将校ただ1人であったのです。
「あなたは処刑の立ち会いにこられた。運のいいことです。しかし現在のところ、この流刑地では、いまのやり方は評判がよくないのです。自分ひとりが例外でありまして、前司令官の衣鉢を継いでいるのは、自分ひとりというありさまなのです」
フランツ・カフカ著, 池内紀訳『変身』(2006)白水社
その異常過ぎる執着もあってか、物語中盤で将校は旅行家に「現司令官の前で処刑機械を使った処刑を支持してほしい」ということを依頼します。
奇妙な機械による処刑を否定的に感じていた旅行家はもちろんその申し出を断ります。すると、将校は捕らえていた処刑人を解放し、処刑機械の中に自らを投げ入れたのです。そして、直前になって壊れてしまった処刑機械によって、一瞬のうちに処刑されてしまったのです。
処刑機械を使って人を処刑し続けていた将校が、処刑機械によって自ら処刑することを選択する、なんとも不気味で奇妙な結末でした。
【解説】『流刑地にて』は破滅の物語なのか
処刑人の身体に針を刻む機械。そして、その機械によって一瞬のうちに処刑された将校。この不条理で衝撃的な物語が意味するものとは一体何なのでしょうか。
作者のカフカは生涯を通して作家とサラリーマンの二足草鞋を履いていました。昼間は保健局の事務員として労働者のために書類を書き、仕事が終わると自室で小説を書く生活。そんな日々をカフカは過ごしていました。
一般的に作家とサラリーマンは異なる存在のように感じますが、カフカにとっては「書く」という行為で共通しており、カフカにとって「書く」という行為とは「創造」と「労働」の二つの側面があったといえます。
カフカはよく労働への苦痛を漏らし、創作の難しさを嘆いていたと言われています。苦しい労働から逃げ出して、好きな創作に打ち込んでも、思ったような作品が書けずに逃げ出した先で苦しむ。それでも「作家として大成したい」という気持ちを密かに抱きながら、こうした日々をカフカは過ごしていたのです。
そのことを踏まえると、作中に登場する処刑機械は「書くこと」のメタファーであり、将校はカフカ自身であると考えることができます。
つまり、処刑機械によって身体に文字を刻まれながらゆっくりと命を奪われることは、カフカ自身が「書く行為」によって感じていた苦しみなのでしょう。そして、将校の最期が意味するものは「処刑機械=書くこと」に魅入られた人間の破滅を暗示していたと言えます。
カフカは41歳という若さで結核により亡くなっていますが、彼は最期まで小説の執筆を続けたと言われています。『流刑地にて』は書くことによって身を滅ぼしたカフカ自身の物語だったのかもしれません。
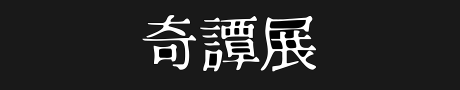



コメント